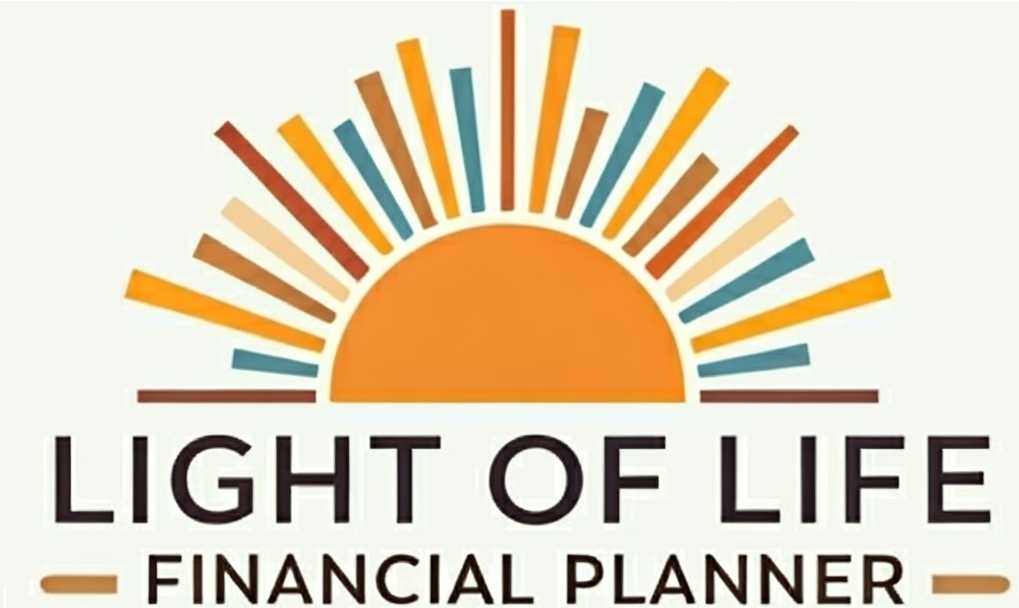ボーナス(賞与)は多くの会社員・公務員にとって年に2回の大きな収入源ですが、「いつ、いくらもらえるのか」「どうやって決まるのか」といった基本的な疑問をお持ちの方も多いでしょう。大阪を拠点とする独立系ファイナンシャルプランナー(FP)の視点から、ボーナスに関する疑問を徹底解説します。

ボーナスと賞与は同じ?
「ボーナス」は英語の「bonus」に由来する言葉で、「賞与」は日本語です。どちらも、企業が従業員に対して、通常の毎月の給与とは別に支払う、臨時の報酬を指します。
国税庁の所得税法などでも、「賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するもの」と定義されており、法律上も同じものとして扱われています。
労働基準法などの法律で、企業にボーナス(賞与)の支給が義務付けられているわけではありません。しかし、就業規則や労働契約に支給に関する定めがある場合は、企業には支給義務が生じます。
ボーナスの支給時期
日本企業の多くは年2回、夏季(6〜7月)と冬季(12月)にボーナスを支給します。具体的には、夏季ボーナスは6月25日前後、冬季ボーナスは12月10日前後に支給される企業が多いようです。
ただし、業種や企業によって異なり、3月決算の企業が多いため、決算確定後の6月に夏季ボーナスが支給されるケースが一般的です。最近では、四半期ごとの業績連動型ボーナスを導入する企業も増えています。正確な支給日は、自社の就業規則や人事部に確認するのが確実です。
国家公務員のボーナス支給日は、人事院規則によって6月30日、12月10日となっています。地方公務員は各自治体の条例により支給日が決められていますが、国家公務員と同じ日付になるケースが多いです。
ボーナスの金額はどう決まる?
ボーナスの金額決定要素は主に以下4つです。
① 企業の業績:前年度や当期の売上・利益
② 個人の業績評価:成果や貢献度
③ 職位や勤続年数
④ 基本給:「基本給×○ヶ月分」という形式が一般的
多くの企業では就業規則や労働協約に算定方法が記載されています。基本給の何か月分かは、企業の状況や個人の評価に左右されるため一概には言えませんが、多くの企業では年間で2ヶ月〜3ヶ月分程度を支給していると考えられます。
手取り額の計算方法
ボーナスの手取り額は、通常、総支給額から以下の項目が差し引かれます。
① 所得税:年収に応じた源泉徴収税率(賞与に対する特別な計算式あり)※注1
② 社会保険料:健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険など
③ その他控除:財形貯蓄、企業年金、社内積立金など
簡易的な目安としては、総支給額の約25〜30%が控除されると考えておくと良いでしょう。例えば100万円のボーナスなら、手取りは約70〜75万円程度になることが多いです。
住民税については、毎月の給与からは毎月差し引かれていますが、ボーナスからは差し引かれません。住民税は前年の所得金額をもとに決定されます。12分割された住民税額が翌年の6月から翌々年の5月にかけて毎月の給与から差し引かれる仕組みです。支給時には住民税の支払はないけれど、ボーナスも所得金額に含まれますので、翌年6月以降に後払いで負担することになります。
ボーナスの賢い活用法
大阪の独立系FPとして常にお客様の利益を最優先に考える立場からは、以下のような活用法をお勧めします。
① 生活防衛資金の確保:6ヶ月分の生活費を現金か普通預金で確保。足りない人はまずここ。
② 高金利の負債の返済:リボ払いやカードローンなどの高金利の借金は早急に返済。
③ 老後に向けた長期の資産形成:iDeCo、NISA、積立投資などを活用して複利効果で長期運用。
④ 中期的な資産運用:ある程度時期のわかる大型支出に対し、それぞれ目的別・時期別に資金を管理・運用する。
例:子供の教育・車の買い替え・住宅修繕・旅行費用・趣味の買い物など
特に現在の世界的なインフレーション環境下では、単なる預金だけでなく、インフレに負けない資産形成が重要です。
ボーナスの使い道に悩んだら、大阪の独立系FP事務所 ライトオブライフにご相談ください。あなたのライフプランの立案から、あなたの望む生き方に合わせた最適な資産活用方法をご提案します。金融商品の販売ノルマに縛られない中立的なアドバイスで、あなたの資産形成をサポートします。ボーナスという貴重な資金を無駄にせず、将来の安心につなげていきましょう。
参考資料
※注1 国税庁 ウェブサイト 「令和7年分 源泉徴収税額表」(賞与) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/15-16.pdf
インフレ税の脅威については、以下のコラムも参考にしてください。
FPの豆知識コラム:『知らず知らずに目減りする?インフレ税の脅威と賢い資産防衛術 – コロナ禍で加速した変化、「2%の目標」、そしてお金の価値を守る方法』
この記事を書いた人
桐山 昌也
株式会社ライトオブライフ 代表取締役 ファイナンシャルプランナー(FP)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)・MBA(経営学修士)
京大卒、銀行・メーカー勤務を経て、現在大阪を中心に独立系ファイナンシャルプランナーとして活動。
「出張型FP」・「最適なアドバイスのできる独立系FP」・「サポートの頼れる実務的FP」・「保険・投資販売しないFP」を特徴としている。
ライフプラン相談・家計改善・資産運用相談は「ライトオブライフのFP」へ https://light-of-life.jp/
株式会社ライトオブライフ 〒545-0035 大阪府大阪市阿倍野区北畠1-1-49 TEL:06-4400-7256
オンライン相談も承ります。